『ドライブ・マイ・カー』の考察
画像参照:映画.com
『ドライブ・マイ・カー』は、村上春樹の同名小説を原作としているほか、劇中劇として演じられた2つの戯曲も重要な要素になっていました。
個人的には、予習するなら原作小説よりもこの2つの戯曲の方が重要度が高いなと感じたほど。
原作の内容は脚本で描かれる一方、戯曲についてはそれ自体の解釈が直接描かれてはいないというのがポイントです。
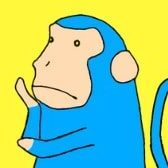
特に『ゴドーを待ちながら』は序盤のごく短いシーンですが、映画全体に関わる方向性が示されていたように感じました。
『ゴドーを待ちながら』というもう一つの戯曲
本作には『ワーニャ叔父さん』のほかにもう一つの名戯曲が登場します。それが『ゴドーを待ちながら』
1952年に発表され、条理演劇の代表作としていまなお上演されている名作です。
『ゴドーを待ちながら』は、2人の浮浪者がゴドーを待ち続ける様子を描いた二幕劇。ストーリー的な展開はほぼないのが特徴のひとつといえます。
1日の終わりにゴドーの使者がおとずれ「彼が今日来ない」ことを告げて一幕は終わり。
2幕でも同様の内容が繰り返され、ゴドーはついに姿を見せず幕を閉じる。
一説には、ゴドー=英語の神(God)とする解釈もありますが、脚本上の明言はなく解釈は観客に委ねられています。
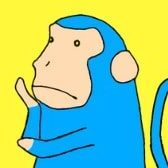
来る保証のないものを待ち続けるという、まさに不条理な状況を描いた戯曲です。
家福は、この劇でも主演の一人である浮浪者を演じていましたが、「何かを求めながら耐えている」彼自身の暗示のような劇中劇となっていました。
妻の不倫に気付かぬふりをし続ける家福の不条理な状況があらわになることで、『ゴドーを待ちながら』がどんどん味わい深く感じられました。
むしろ物語が進むにつれて音、高槻、みさき、そのほかの登場人物までも含めたそれぞれが抱える葛藤をも暗示していたように思えてきて、ワーニャ叔父さんに並ぶ存在感が残りました。
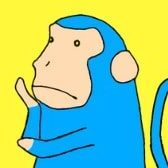
冒頭に『ゴドーを待ちながら』が差し込まれた意味がストーリーが進むほど深く刺さり、脚本の妙にも脱帽です。
多言語演劇
家福が手がける演出法として登場する多言語演劇は、実際の舞台演劇の現場でも取り組まれているもののひとつです。
コミュニケーションを多角的にとらえるきっかけとして興味深い演出法だと思うのですが、本作からは2つのことを感じました。
2.他者を理解したという願い(希望的な視点)
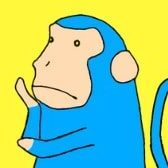
手話で演じられる静かなシーンと差し込む日の光が印象的でした!
なぜ家福はワーニャを高槻に演じさせたのか?
画像参照:映画.com
メインエピソードとなる『ワーニャ叔父さん』の劇中劇は、家福ではなく高槻が演じる予定でした。高槻自身も疑問をもったこの配役には家福のどんな思いがあったのか。
のちのち家福自身が、ワーニャを演じることに限界を感じていることも語られていますが、もう一つの理由に真意があるようにわたしには思えました。
それはもう単純に仕返し!
家福は日常から、自分の気持ちまでも演じて偽っていました。妻の不倫現場を目撃して顔色ひとつ変えない代わりに、目薬で涙を流すシーンがそれを象徴しています。
もちろん限界というのも本音だとは思うのですが、本作のキーワードにもなっている「演技と裏にある本音」というフィルターで観ると、語られない本音として仕返しの気持ちがあったように思えます。
ストーリー的にも舞台が東京から広島へと移り、家福の本当の感情がこれから徐々に出てくる前兆のようにもみえて興奮したエピソードでした。
家福とみさき/ワーニャとソーニャ
画像参照:映画.com
家福とみさきが上十二滝村で抱き合うシーンは、ワーニャ叔父さんの戯曲のラストシーンを彷彿とさせる場面でした。
ここで多くが語られることがないですが、繋がる劇中劇のラストシーンはそのまま2人のたどり着いた答えであるように感じられます。
画像参照:映画.com
家福が演じたワーニャ叔父さんを観劇するみさきの服が舞台上のソーニャと同じ青色だったことも印象的な演出でした。
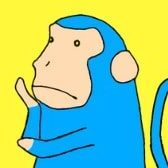
家福とみさきは、自分たちの苦悩に耐えながら生きていくことを受け入れたんですね。
ラストシーンの解釈
画像参照:映画.com
みさきが赤いサーブ900を運転するラストシーンは、人によって解釈があると思います。
個人的には2人の関係は良好に続いているのだと感じました。もしかすると、家福がみさきを専属ドライバーとして採用し、海外公演にも帯同させているのかもしれません。
サーブ900は家福とみさきの繋がりそのものの象徴ですし、同乗していた犬はユンス夫婦のシーンから家族のモチーフのように感じ取ることができました。
そこから、歳を重ねた親子のような距離感で家福とみさきの関係が続いている妄想が膨らみます。
戯曲『ワーニャ叔父さん』には、生きていくことの象徴として「仕事」とい言葉が多く登場しており、本作の家福やみさきも「仕事」という言葉を何度も口にしていました。
だからこそ、人生を歩んでいくことを決意した二人が、それぞれの仕事を一生懸命こなしている少し先の未来として描かれたラストシーンのように私にはみえたのです。
コロナ禍の韓国を描いたシーンも差し込まれますが、舞台芸術にとって困難な状況が続く昨今の状況を考えると、苦難の中でも芸術の文化を絶やさない意志を投影したラストシーンと捉えることもできると思います。
“耐え抜いた先の希望”は、『ワーニャ叔父さん』のテキストで描かれていますし、その戯曲を海外でも演じる家福の姿がもしあるなら、それはまさにコロナ禍の世界に向けられた濱口監督からのメッセージなのではないでしょうか。
『ドライブ・マイ・カー』考察まとめ
冒頭のゴドーで示された「不条理な人間世界」
ワーニャ叔父さんを下敷きに描かれた「忍耐から希望への物語」
多言語演劇によって、表現される「コミュニケーションの本質」
これらを過不足なく映画の中に織り交ぜ成立させた上で、繊細な物語に昇華させている。
とても緻密なのにどこか実験的な雰囲気も感じられて、その緊張感をたもったままラストシーンまでスクリーンに惹きつけられていました。
あっという間ではないけど、過不足のない3時間という印象の映画でした。
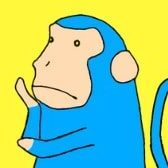
パンフレットは今からでも入手できますよ!








コメント