【関連】NGな子どものほめかたとは?児童発達学博士に学ぶ上手なほめ方【徹底解説】
【関連】いい子症候群になる原因は?親の特徴と3つの改善策

私はAmazon prime readingで読ませていただきました。
罰を与える叱り方がNGな4つの理由

罰を与えるやり方は、子どものしつけでよくみられる光景ではないでしょうか。
「いい加減にしないと叩くよ」なんて言葉を以前耳にしたこともあります。
暴力はもちろんだめですが、それ以外でも罰を与えるやり方がNGな理由が4つあります。
1.子どもの攻撃性をひきだす
罰を与えることは、子どもの攻撃的な行動を促す恐れがあります。
親と子どもの力関係を想像してみてください。
罰を与えられると、子どもは逃げ場がなくなってしまいます。
さらに、罰を与える相手(親)に対して不満をもつようになります。この不満を攻撃的な行動で表現するようになるのです。
子どもの攻撃的な態度に、さらに罰を与えることで負の連鎖となってしまう可能性もあります。
2.暴力や圧力の正当化につながる
罰を与えることは、暴力や圧力で問題解決をする親の姿を子どもに見せているのと同じです。
親の暴力を経験すると、親になってから同じことを繰り返すということもいわれています。
問題にぶつかったとき、平和な方法で解決できる力を育むためにも、暴力や圧力はNGです。
3.親子関係が傷つく
罰を与える親は子どもにとって安心できる存在と感じられなくなります。
親への安心がなくなることは、親子の信頼関係にも影響があります。
親子の信頼関係に傷がついた状態が続けば、子どもが心を閉ざしてしまうことも。
子どもが親に安心感を抱ける関係性は大切です。
4.反省につながらない
罰を与えられた子どもは、次は罰を避けようと考えます。
罰を避けることに意識がむくことで、何がわるかったのかを考えなくなることも。
行動と罰のつながりを子どもが理解できなければ、反省は促されないです。
罰を与える行為で、アメとムチというものもありますが、こちらも注意が必要です。
アメとムチ、避けるべき理由
罰を与えることにも共通しますが「アメとムチ」のように子どもをコントロール下に置くようなやり方にも注意が必要です。
1.与え続けなければいけない
アメとムチは与え続けることでしか効果を得られません。
ムチを与えても、反省がなければ同じことを繰り返すだけです。
反対にアメを与えたとしても、アメのためにやるということになります。
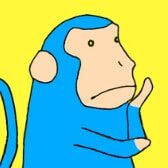
行動とアメ(ムチ)が結びついたらさいご、与え続けなければなりません。
2.自己中心的な考え方に育つ
アメとムチでコントロールされつづけると、自分の行動が相手に与える影響を考えられなくなります。
アメをもらう(またはムチを避ける)自分の行動に意識が向くと、相手への影響を考えられなくなるので危険です。
結果として自己中心的な考え方を育てることにつながってしまいます。
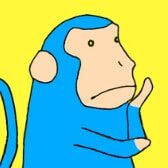
こういった状況を回避するためにも上手な叱り方を身につけることも有効です。
上手な叱り方4つのポイント

これまでのNGポイントを踏まえたうえで、上手な叱り方を紹介します。ポイントは4つです。
1.「ダメ」「違う」はなるべく使わない
子どもには、否定的な言葉を伝えないようにすることが大切です。
子どもの気持ちを受け入れることから始めると、子どもも身構えることなく親の話を聞くことができます。
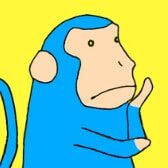
子どもの気持ちを否定せず「ありのままを受け止めるよ」と伝えるのがポイントです。
2.プロセスに目を向ける
結果までの努力や、やり方にフィードバックをすることが重要です。人中心の叱り方は、避けます。
やり方や努力に対してネガティブな評価をせずに、具体的なフィードバックをすることが大切です。
3.叱る理由を説明する
子どもの行動が、自分や相手にどんな影響があるのかを具体的に説明します。
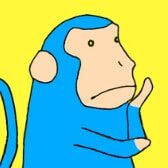
「ダメ」の一言にせず、なぜダメなのか理由を具体的に伝えることが大切です。
4.気持ちを伝える
子どもを否定せず、親の気持ちを伝えてコミュニケーションをとります。
このコミュニケーション方法は『自分でできる子に育つほめ方叱り方』の中で、アイメッセージとして紹介されています。
アイメッセージの4ステップ 行動+感情+影響+提案
感情:親や周りがどう思ったかを伝える。
影響:親や周りにどんな影響があるか伝える(どんな問題があるか伝える)
提案:どうしたら同じできごとを避けられるか、解決策を提案する。
親の気持ちを中心に解決策を提案していくことがポイントです。
詳しくは、こちらの解説記事でご覧ください。

まとめ
今回ご紹介した方法はあくまで1つの方法論です。
無理にすべてをマスターする必要もないと思います。
なにより、親自身に無理のない範囲でできるのが一番大切です。
できる時にできるものだけ、くらいの気持ちで知っておいていただければと思います。
おしまい
【関連】






コメント