作品紹介
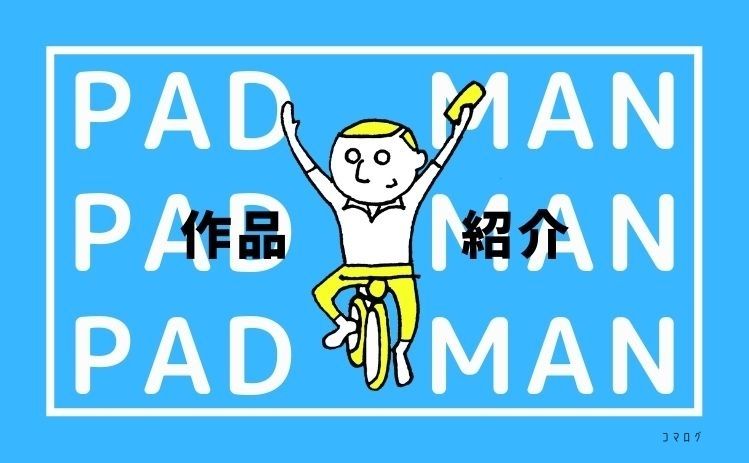
パッドマン(原題:PADMAN)は、2018年にインドで制作され、日本でも公開されました。
たった一人で女性用 生理用品を作りあげ、5億人のインド人女性を救った男性の物語です。
あらすじ
新婚のラクシュミは、新妻であるガヤトリにべた惚れ。あの手この手で愛情を捧げていました。
そんなある日、彼は生理中の妻のために、生理用ナプキン(パッド)を買いに行きます。いまだ生理がタブーとされるインドで、男が生理用品を買うのはひと苦労。やっとの思いで手に入れたものの、あまりに高額なため、妻には断られてしまう。
そこで、ラクシュミは安価なパッドを自らの手で作ることを思いつく。
作品情報
【キャスト】
ラクシュミ アクシャイ・クマール
パリー ソーナム・カプール
ガヤトリ ラーディカー・アープテー
【スタッフ】
監督・脚本 R・バールキ
撮影 P・C・スリーラム
音楽 アミット・トリベディ
解説
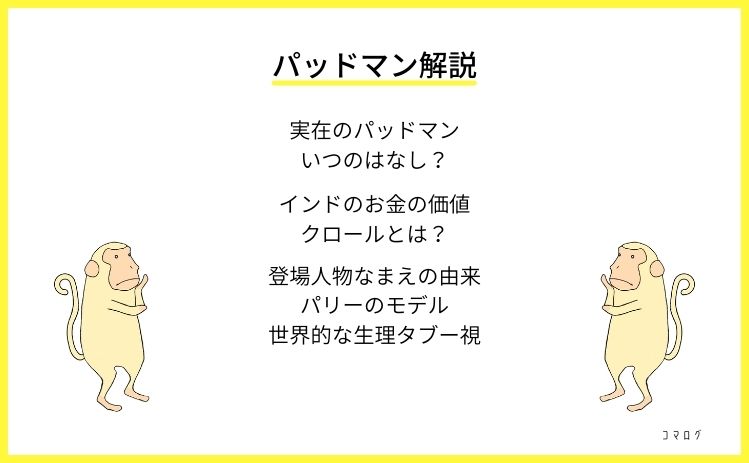
本作の主人公ラクシュミは、実在の人物がモデルとなっています。
実在のパッドマン「アルナーチャラム・ムルガナンダム」
アルナーチャラム・ムルガナンダム/Arunachalam Muruganatham
タミル・ナードゥ州コインバトール生まれ
2014年米タイムズ紙の「世界で最も影響のある100人」選出
2016年インド政府より褒章パドマシュリを授与
機織り職人の父を、幼いころに交通事故で失い、母親に育てられる。学校は14歳までしか通えず、以降はさまざまな職に就いていた。結婚を機にインド女性の生理の実態に衝撃を受ける。生理用ナプキンの値段の高さも知り、自作のナプキン製造に乗り出す。作中でも語られるように、生理へのタブー視がいまだ残るインドにおいて、彼の行動は異常そのものでした。実際に妻との離婚話もあったことは、ムルガナンダム氏のスピーチの中でも語られています。2006年チェンナイのインド工科大学で草の根テクノロジー発明賞を受賞。以降は社会実業家として、女性の自助グループへのマシンの販売を通し、女性の意改革や社会進出に貢献。インドにとどまらず世界各地へと広がりを見せる活動となっています。
つづいて、作中に出てくる数字の解説です。
物語を楽しむ参考にしていただけたら幸いです。
いつのはなし?
映画のオープニング時は2001年です。ラクシュミのパッドマシン制作期間は、作中の金貸しのセリフから1年以上は経過していることが分かります。現実の話を調べるとインド工科大学での発明賞受賞は2006年となっているので、マシン完成までに5年近い年月が立っていることになります。映画はかなりテンポよく進んでいますが、5年の歳月がかかっていると思って観ると印象が変わってくるのではないでしょうか。
インドのお金の価値は?

1ルピーは約1.5円(本稿執筆現在)。作中のパッドの値段55ルピーに換算すると約82円です。安く感じるかもしれませんが、インドの大卒の初任給は約4万2千円。教育を受けられない農村などでは半分以下になります。仮に月収が1万5千円とすると、1日500円で家族を養わなくてはいけません。こう考えると2001年当時の生理用品がいかに高額だったかが分かりますね。これでは、どんなに家計をやりくりしても厳しいはずです。
ちなみに、日本にも同じような時代はありました。田中ひかるさんの著書「生理用品の社会史」角川ソフィア文庫によると、1904年に発表され日本での生理用品の先駆けであった「衛生帯」の価格は30銭でした。日雇い労働者の日当が40銭の時代の話です。これでも100以上年前の話ですから、インドとの時代差は驚きです。
数クロールはいくら?
クロールはインドのお金の単位で、1クロール=1000ルピーを表します。ラクシュミが家政婦として雇われていた大学教授が、生理用品の製造マシンの値段を説明するシーンのなかに「数クロール」というセリフがありますが、マシンは数千万円するということです。その後、ラクシュミの開発するマシンが、9万ルピー(約9万円)ですから、純粋な制作費だけで比較しても破格の安さであるとことがわかります。
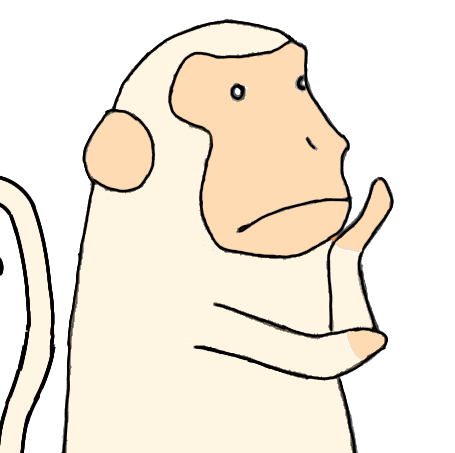
まさに価格破壊です。
次に人物についても触れておこうとおもいます。
登場人物の名前
ラクシュミ
主人公ラクシュミの名前は、美と豊かさの女神ラクシュミからとられています。ヒンドゥー教最高神の1人ヴィシュヌの妻とれています。主人公の名前からして、女性や妻を語る気満々のネーミングです。
ガヤトリ
ラクシュミの妻であるガヤトリの名前も、ヒンドゥー教からとられています。ガーヤトリー・マントラとうヒンドゥー教最高峰のマントラがあり、太陽神サヴィトリへの讃歌であると同時に、ガーヤトリー自体も神格化されています。神格化されたガーヤトリーは女神であるとされています。やはりこちらも女神なんですね。
パリー
パリーは、インドで「妖精」という意味があります。ほか二人の主要人物が神の名前から取られていることを考えると、すこし異なる立ち位置を与えられていることがわかります。
パリーは実在する?モデルは?
パリーは映画オリジナルのキャラクターのため実在しない人物です。映画制作にあたって作られたということで、監督の意図を投影したキャラクターと言えるでしょう。どのような演出で登場するのか気になる役どころです。
さいごに、物語のキーワードでもある女性の生理タブー視について簡単に。
世界的にみられる生理タブー視
作中に登場するような女性の生理に対するタブー視は、世界各地にみられます。多くの場合、生理期間中の女性を穢れ(ケガレ)とし、衣食住を家族と分ける風習がみられます。いまは全世界的に、廃止への動きがありますが、風習を断ち切ることは一筋縄ではいかないようです。
さきに取り上げた田中ひかるさんの著書「生理用品の社会史」角川ソフィア文庫によると、日本にも「他屋」や「他火」といわれる同様の風習がありました。1970年においてもなおその風習が残る地域もあったとする研究報告もあります。
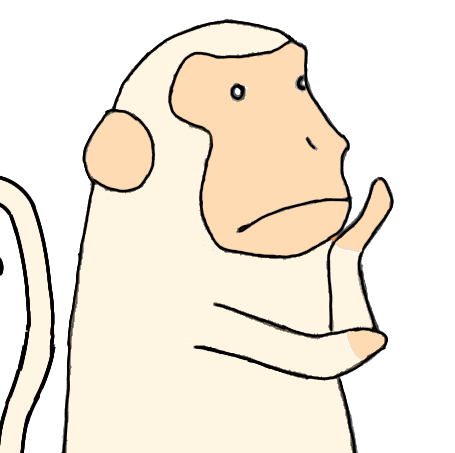
むかしからの風習とはいえ、現代においてはあきらかな差別。
本作は、そのような差別と向き合うお話でもあります。
レビュー
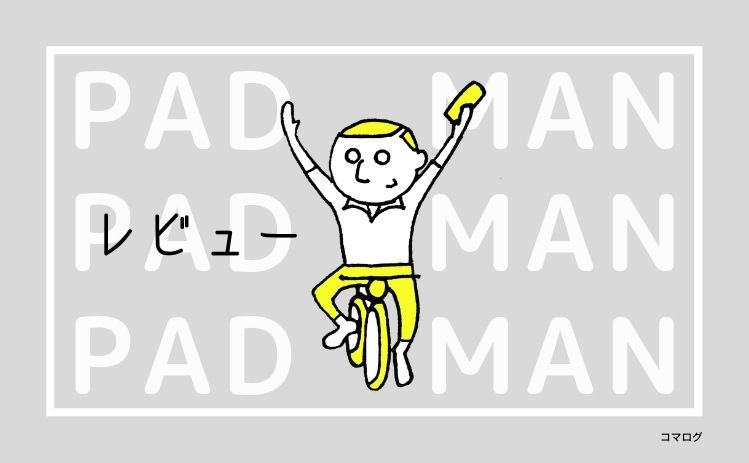
異常者を生みだす非常識な社会
インドの文化や風習に対する批判的な態度は間違いなくこの映画のテーマです。社会や風習が生み出す盲目的な常識によって決定された非常識なレッテルが、あっという間にラクシュミを社会の外れものにしてく序盤。見ているだけで辛いです。
作中、ラクシュミが異常者のレッテルを貼られた原因は、彼の住む村や社会にありました。現代の日本に暮らす私達からみれば、ラクシュミの心意気は当たり前に受け入れられそうなのものです。しかし、いまだ生理がタブー視されるインドでは難しい。繰り返しになりますが、2001年の話ですからね、本来なら否定的な意見を持つ方が難しいと考えてしまいます。
実際、ラクシュミは愛する妻や妹たちの苦労や衛生的な危険性を知ったが故に奮闘していました。しかし、彼が人道的になればなるほど、文化や習慣との溝は深まるばかり。ラクシュミが孤立していく前半パートは見ていて非常に辛い時間でした。
ラクシュミの活動と対比される象徴として神様や聖者が何度も登場していたのも印象的でしたね。インドの若者は当時何を感じたのでしょか。機会があればインタビューしてみたいです。
当たり前を求め続けた純粋な気持ち
ラクシュミはただ、妻ガヤトリや、妻のような女性たちに当たり前のこととして生理用品を普及させることを求め続けました。作中のセリフにもあったように、彼にとってそれは男として当たり前の責任でした。そんな彼の言動に、ついつい目が潤んでしまいました。なぜなら、そんな当たり前のためにラクシュミが払った犠牲は、あまりにも辛すぎるものだったからです。
愛する妻と離れ、親姉妹にも見放され、母親にいたっては彼を「狂人」扱いする言葉まで放ちました。それでもあきらめず「当たり前」のために不条理な社会に挑んだ彼の想いを想像するだけで、また胸が熱くなります。この映画自体も、そんな彼の想いの延長線上で生まれたことは、記憶にとどめておきたいところです。
「パリー」の存在
パリーの演出については製作者の都合強すぎ感がぬぐえませんでした。主にはラブロマンス的演出について。パリーは、映画オリジナルのキャラクターですから、当然、監督や脚本にとって都合のいい存在です。しかし、観客にまでいい影響を与えたのでしょうか。
恋愛要素を持ち込んだことで、脚本上はドラマチックになったでしょう(それすら疑問ですが)。ラクシュミの人間的な魅力をみせる演出ということなら、男女の恋愛感情に頼らなくてもよかったのでは。あとでも書きますが、パリーをインドの近代的な女性像として際立たせるうえでも特に必然性のない演出だったと思いました。終盤の空港での一幕を見た後では、奥さんとの復縁を心から祝福する気持ちにはなませんでしたし、ラストに少ししこりが残ります。
一方で近代的な女性像としてバリーという存在を描きたかったという点は納得できます。前時代的な妻ガヤトリと対をなす存在としてのパリーは物語を構造から支えている重要人物でした。特にパリーとラクシュミが初めて出会うシーンは、ラクシュミの人生観とその先の展開を示唆するような名場面でしたね。妻ガヤトリとの対比を精神性や思想的な部分にとどめておいてくれれば、ラストシーンまで疑問なく観れたように思います。
クライマックスの国連スピーチ
本作のクライマックス、国連でのスピーチは、教育・啓蒙映画としても本作が有益な物語であることをあらためて明確にしたシーンだったと思います。国連への招待は、ラクシュミにとって当初の目的を達成したあとの話です。サクセス・ストーリーとしてのラクシュミの物語は、自助団体の運営で終わってもよかったはずでした。しかし、サクセス・ストーリーで終わらせず、ラクシュミであり実在のパッドマンであるムルガナンダム氏からのメッセージが、私たち観客に届けられたことにまた感動しました。ここにこの映画のもう一つの価値があると思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
カルチャーショックもあり、考えさせられる内容。
教育映画としても、この先ながく影響を持つ映画なんだろうなと思いました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
おしまい。

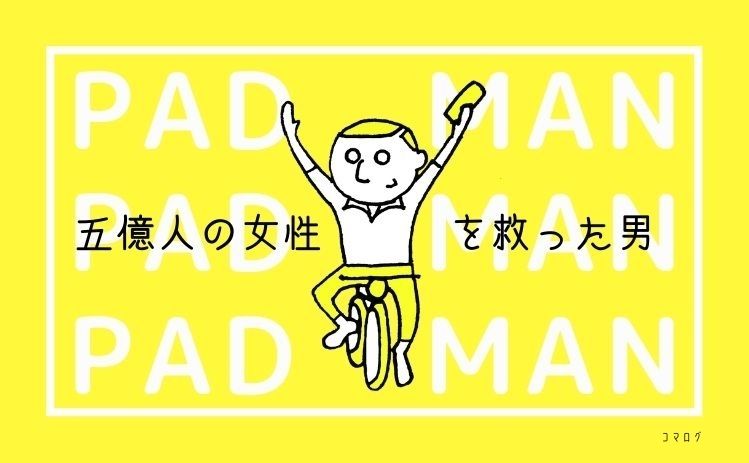


コメント